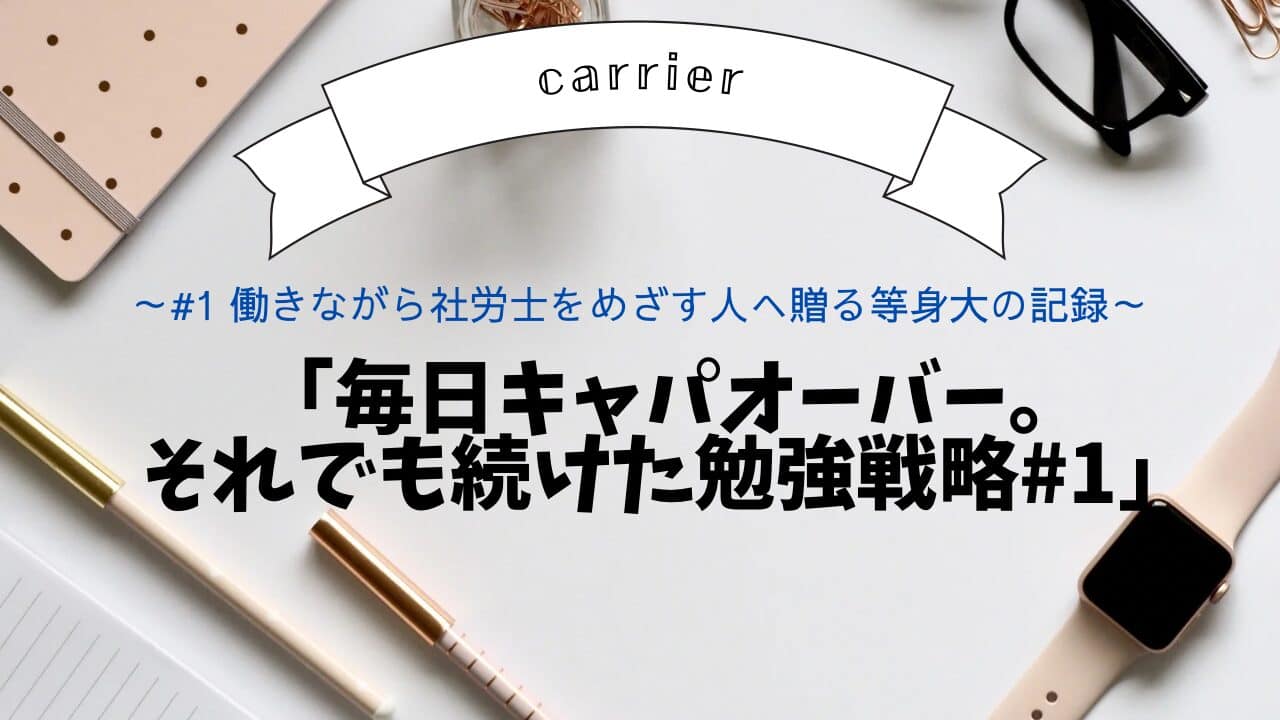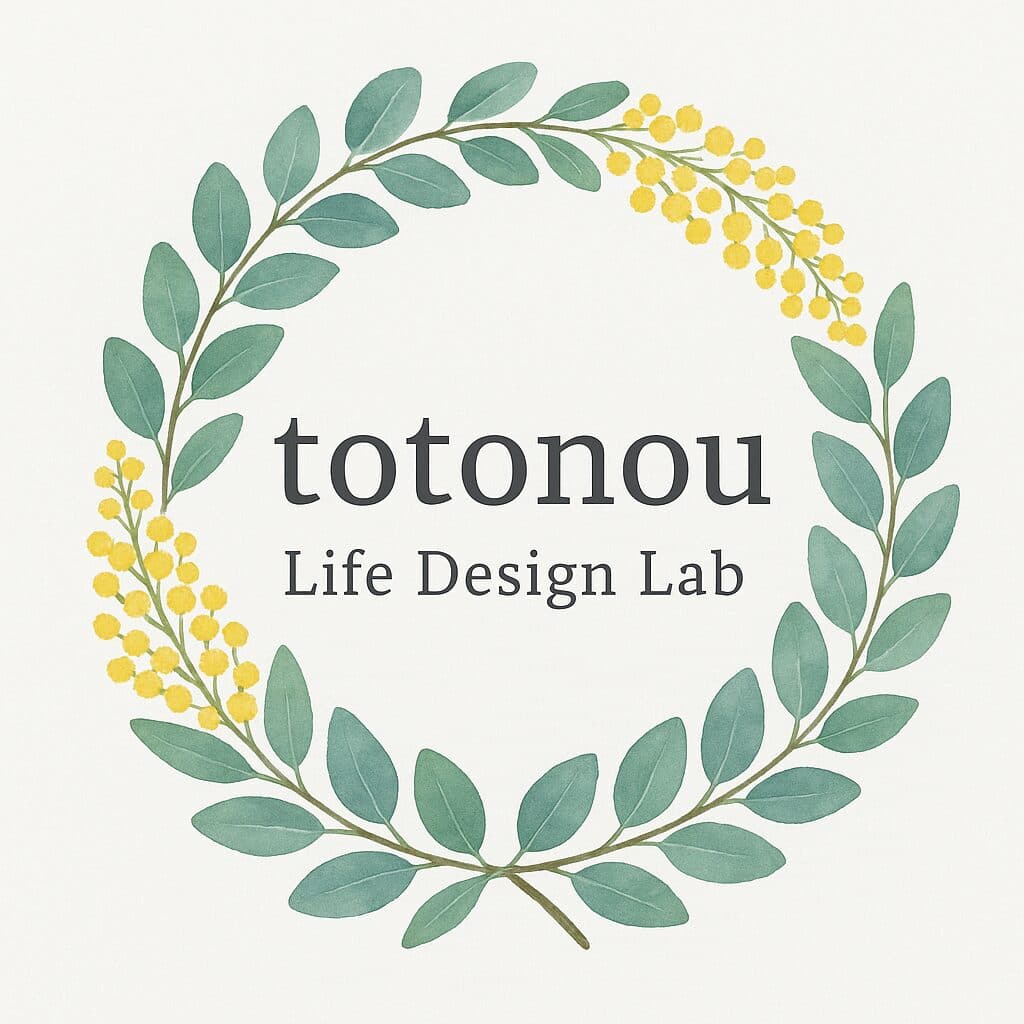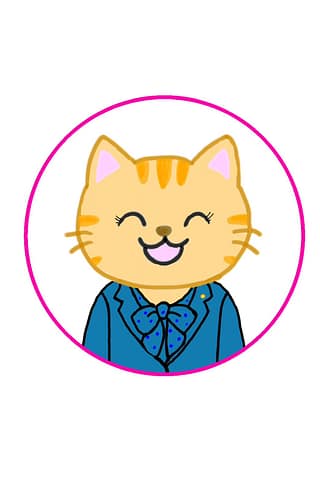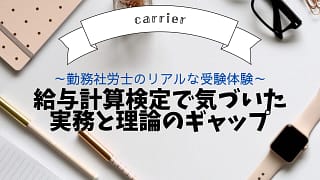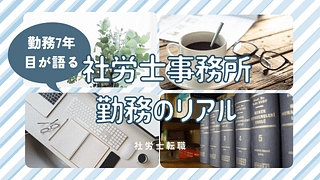毎日キャパオーバー。それでも続けた勉強戦略#1
働きながら社労士をめざす人へ贈る等身大の記録
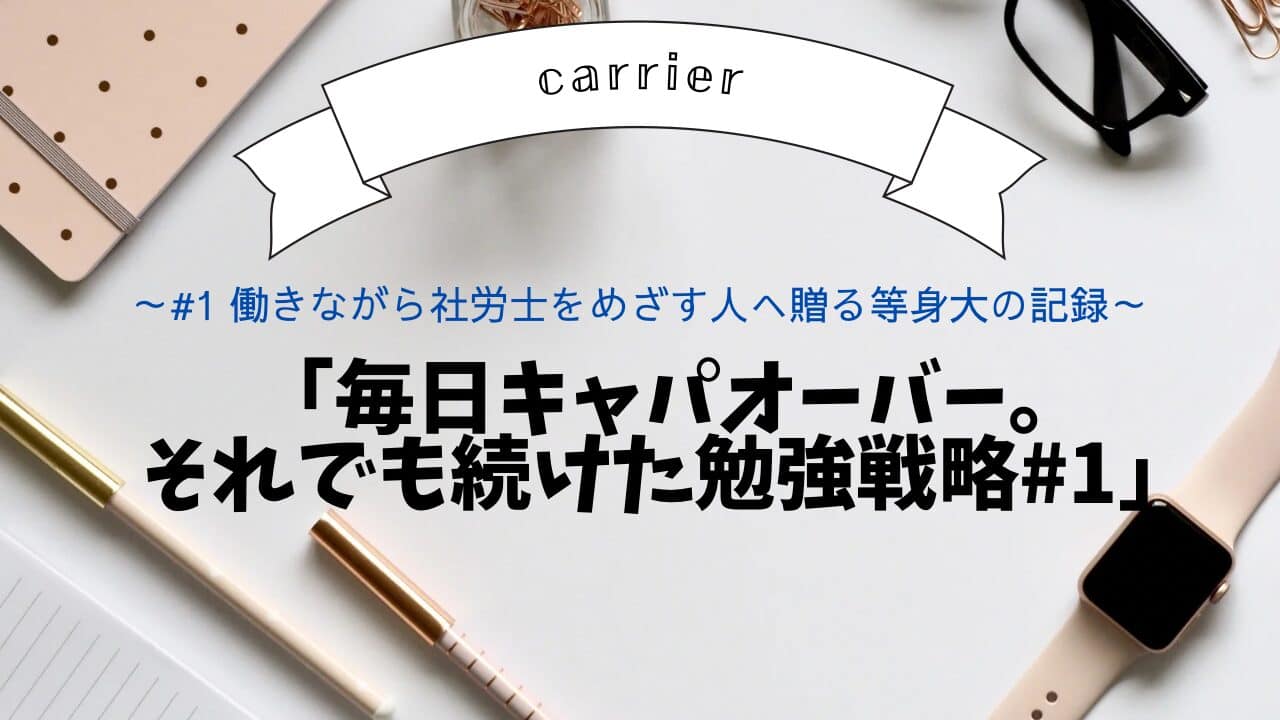
「フルタイム勤務で子育て中。それでも、社労士に合格できました。」
…なんてよくあるタイトルだけど、そんなにうまくいったわけじゃありません。
何年もかかったし、途中で何度も心が折れそうになったし、泣きながら過去問を開いた日もありました。
だからこそ言いたいのは、「資格勉強に向き合っている時点で、もうすでにすごい」ってこと。
これは、そんな頑張っているあなたの参考にはならないけど、寄り添いたい記録です。
どうか気楽に、気分転換のつもりで読んでいってくださいね。
1. 実務も家事も忙しい中で、どうやって合格できた?
社労士事務所での実務、家事、育児。やることが山ほどある中で、どうやって社労士試験に合格できたのか?とよく聞かれます。
私にとっての一番の転機は、職場に試験を受けることを宣言したことでした。
それは「応援してもらうため」というよりも、自分にプレッシャーをかける『自戒』の意味が大きかったんです。
職場も快く応援してくれて、「8月に試験あるんだよね」と気にかけてもらえる環境に。
直前期は仕事量も調整してもらえていました。休憩室を自習室として使用することもでき、恵まれた環境にあったと思います。
宣言のおかげで、自分自身も気を抜かずにタイムマネジメントを意識できました。そしてもちろん、家族の協力も欠かせません。子どもとの時間は短くても質を大事にして、「今この時間は全力で楽しむ」と決めていました。
勉強時間はスキマ時間がメイン。
でもその代わり、「何をやるか」をあらかじめ決めておくことが超重要!
まとまった時間が取れない分、段取りと計画でカバーしていました。1週間単位で学習計画を立てて、日々タイムマネジメントを調整していく。この『微調整力』こそ、働きながら合格するためのカギだったと思います。
2.なぜ“働きながら合格”をめざしたのか?
「仕事を辞めて勉強に専念した方がいいのかな?」
受験を決めたとき、一瞬そんな考えも頭をよぎりました。でも、私にとって“働きながら”は選択ではなく、前提でした。生活のため。家族のため。辞めるという選択肢はなかったんです。
もちろん、働きながらの受験には大変なことがたくさんあります。
- まとまった勉強時間がとれない
- 仕事で疲れ果てて、夜は集中できない
- 急な残業や家庭の用事で計画が狂うこともしばしば…
でも、働きながら受験することにはメリットもありました。
- 日々の実務とつながることで、知識が定着しやすい
- 時間が限られているからこそ、勉強の優先順位が明確になる
- 「時間がないなりに工夫する力」が自然と身につく
時間が限られているからこそ、「この時間で必ずやる」という集中力が自然と身につきました。時間が多すぎるとだらだらしがちですが、フルタイム勤務があることで、むしろメリハリのある学習ができたんです!
3.スケジュールの立て方(科目ごとの配分&月別計画)
通信講座を使って勉強していた私が、最初に意識していたのは
「通学スタイルの学習スケジュールに追いていかれないこと」でした。
通信はどうしても“自分次第”になりがち。でもだからこそ、「ペース管理」が肝。
ここでは、私が実際に立てていたスケジュールと学習のポイントをご紹介します。
【9月〜5月上旬】基礎固め期間
- 過去問をひたすら繰り返して、正答率を上げることに集中
- 判例は1日1つでもOK。毎日少しずつ触れることで習慣化
- 労一・社一は、日曜の朝(ニチアサの時間帯)にルーティン化
- メイン学習中の苦手な論点は大きなふせんに書き出して壁に貼る → 可視化して意識づけ
- 学習が終わった科目のふせんは、復習用ノートとして保管
【5月〜7月】直前期対策スタート
- 演習問題を本格的に開始。模試もこの時期に受ける
- 模試は「順位や点数」より復習が命!
- 間違えた問題、曖昧だった論点から自分の弱点を把握する
- 1週間ごとに計画を見直して調整。復習時間も確保しながら進める
【8月】試験直前期
- 最優先は体調管理とメンタル維持!
- 世間では「選択式対策」が盛んになる時期だけど、私は択一が安定するまで択一対策重視!
→ 択一の50点の壁を突破がカギ!「択一7:選択3」のバランスに - 教材は追加せず、今ある教材を信じて繰り返す
- 音声学習で総復習+テキスト読み
- 気になる論点はふせんでピックアップして、**当日持っていく「まとめノート」**に集約
働きながらだと、「完璧な計画」はなかなか実行できません。
だからこそ、**“完璧じゃなくても前に進めるスケジュール”**を作ることが大切。
自分のペースを知って、計画を立てて、必要ならどんどん修正していく。
これが、長期戦を乗り切るためのコツでした。
私は大原の通信講座で学習していました。9月から試験前日まで、通学コースと同じペースで進められる教材とスケジュールが組まれていて安心でした。具体的な教材については#2の記事でご紹介します!
4.平日ルーティン 勉強スケジュール(朝・通勤・昼・夜の使い方)
| 時間帯 | 学習内容 |
| 4:00~6:00 | メイン科目の過去問演習/判例読み。1日の集中タイム! |
| 通勤時間 | 運転中はサブ科目の音声講義を聞き流し。就業前の15分は「毎日年金!一問一答アプリ」で脳をウォームアップ |
| 昼休み | 秒トレ(短時間トレーニング)でスキマ勉強。軽食しながらでもOK! |
| 退勤~夜 | 子どもとの時間を最優先。家事・育児のすき間に音声学習で復習。 |
| 21:30~23:00 | 子どもが寝た後、講義視聴&朝の続きの過去問演習 |
| 就寝前 | 手帳にその日の学習内容&勉強時間を記録し、達成感で1日を締めくくる |
平日は4時間、土日は6時間以上。時間は“スキマの積み重ね”
子育てとフルタイム勤務の両立の中で、平日は1日4時間前後の勉強時間を確保していました。「そんなに取れるの!?」と思われるかもしれませんが、コツは**“スキマ時間の積み重ね”**。
朝の2時間、通勤中、昼休み、夜の1時間…。
まとまった時間がとれなくても、1日のうちに少しずつ積んでいけば、大きな時間になります。
土日は、最低6時間、直前期は10時間勉強する日もありました。
もちろん、家族との時間も大切にしたい。だからこそ、**「どこで集中して、どこで休むか」**のメリハリを大事にしていました。
ここまでできたのは、家族の協力があってこそ。
「子どもと過ごす時間は全力で楽しむ」「家族に感謝を伝える」など、小さな積み重ねも大切にしていました。
5.モチベ維持のコツ(不安やスランプとの向き合い方)
働きながらの勉強は、ただでさえ時間も体力もギリギリ。
「落ちたらどうしよう」「こんなに頑張って意味あるの?」そんな不安が、ふとした時に心をよぎることもありました。
でも、不安を抱えているのはあなただけじゃない
*“頑張ってるのに不安”**なのは、それだけ真剣だからこそです。
私が実際にやってよかったのは、
SNSで“勉強アカウント”を作って、受験生仲間や合格者や先生とつながること。
- 今日の勉強報告
- 不安な気持ちの吐き出し
- 仲間の「おつかれさま」に救われた日も
孤独な戦いを、一緒に頑張る仲間がいる場所に変えるだけで、心が軽くなります。
私はX(Twitter)で勉強アカウントを作って、毎日の学習記録をポストする習慣をつけていました。合格後も、Xで出会った仲間との交流が続いていて、本当に良かったと思います。縦のつながりだけでなく、横のつながりができたことは大きな財産になりました!
6.【まとめ】「完璧じゃなくても、続ければ合格できる」
フルタイム勤務、家事、育児…時間も体力も限られる中での受験勉強は、
決して簡単な道のりではありません。
でも、「働きながらでも合格できる」ということを、私は身をもって実感しました。
- 完璧を目指さず、スキマ時間を積み重ねること
- 柔軟に計画を調整して、前に進み続けること
- 応援してくれる人や仲間を大切にすること
どれも、特別なスキルが必要なわけではありません。
「続ける工夫」と「支えてくれる人」さえあれば、あなたにもきっとできるはず。
大丈夫、あなたの努力はちゃんと力になっている。
今日も1問、解いてみましょう。小さな一歩が、必ず合格につながります!