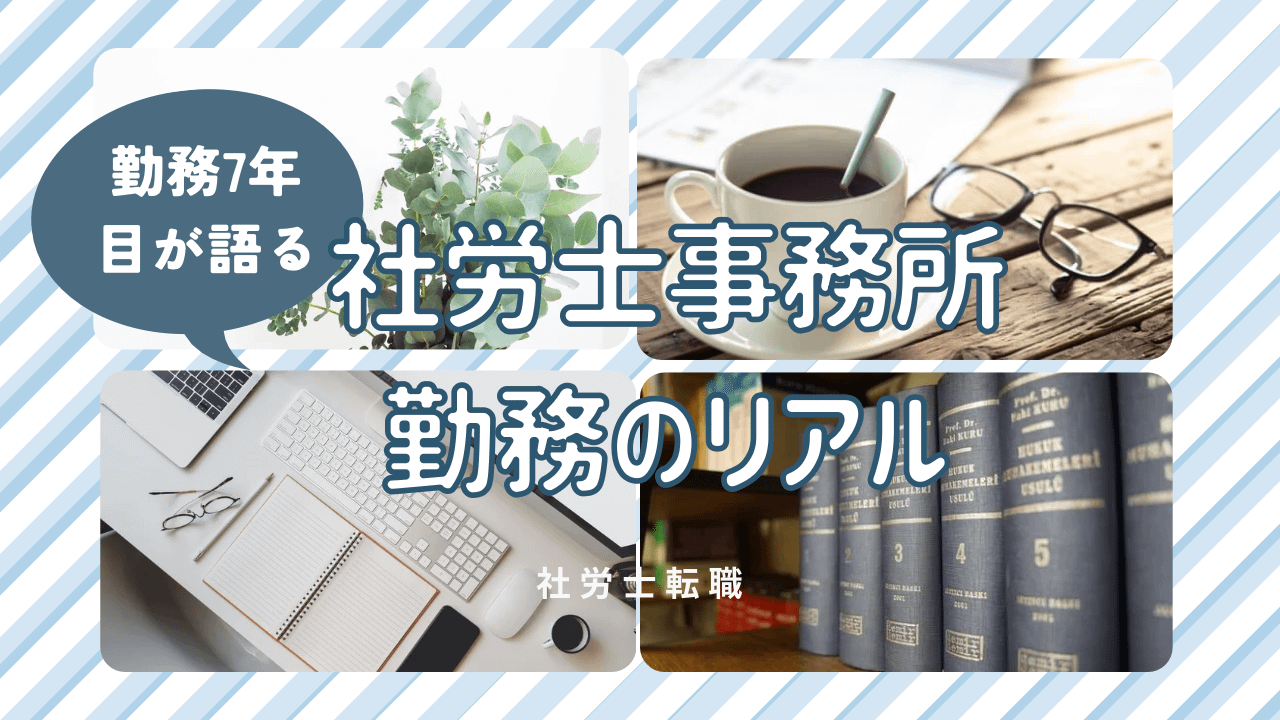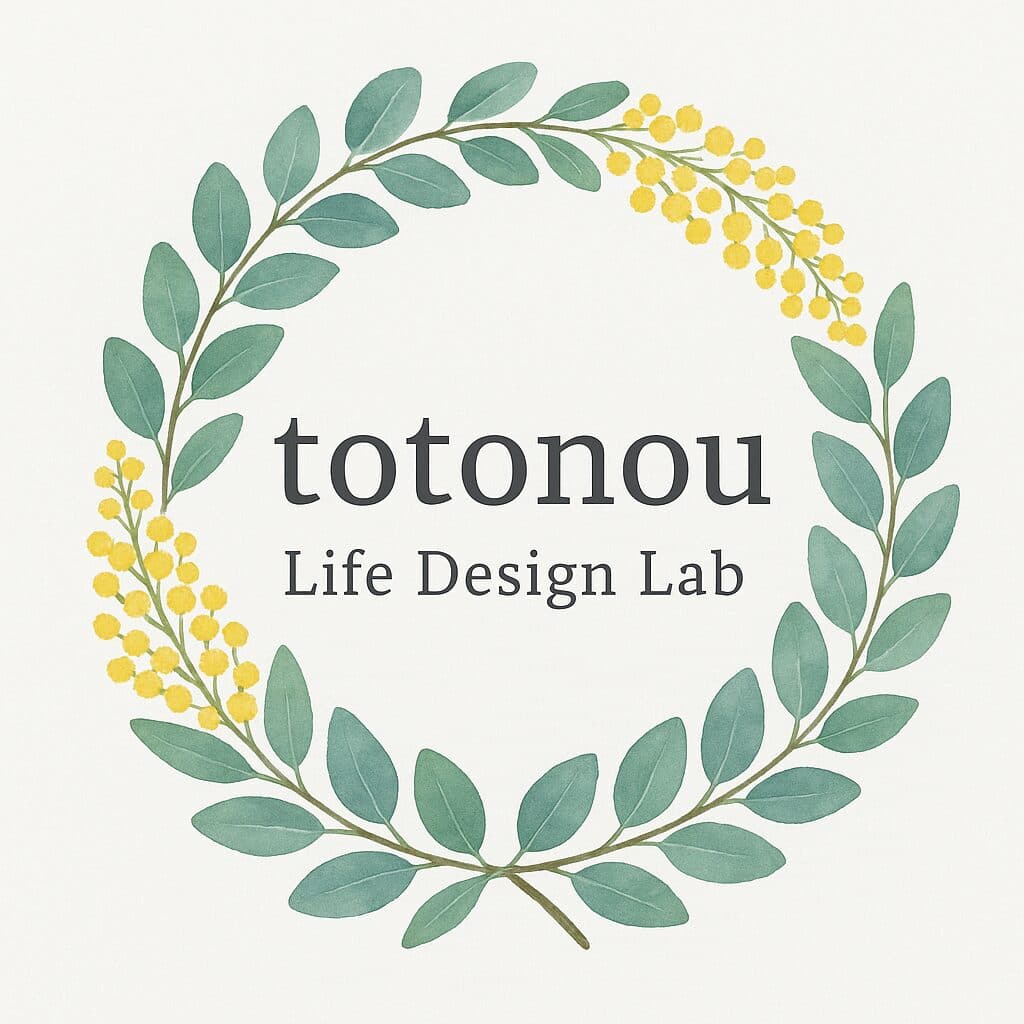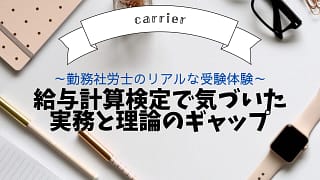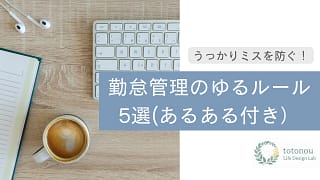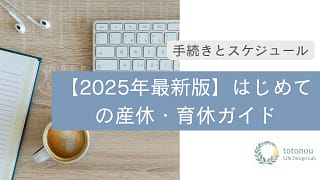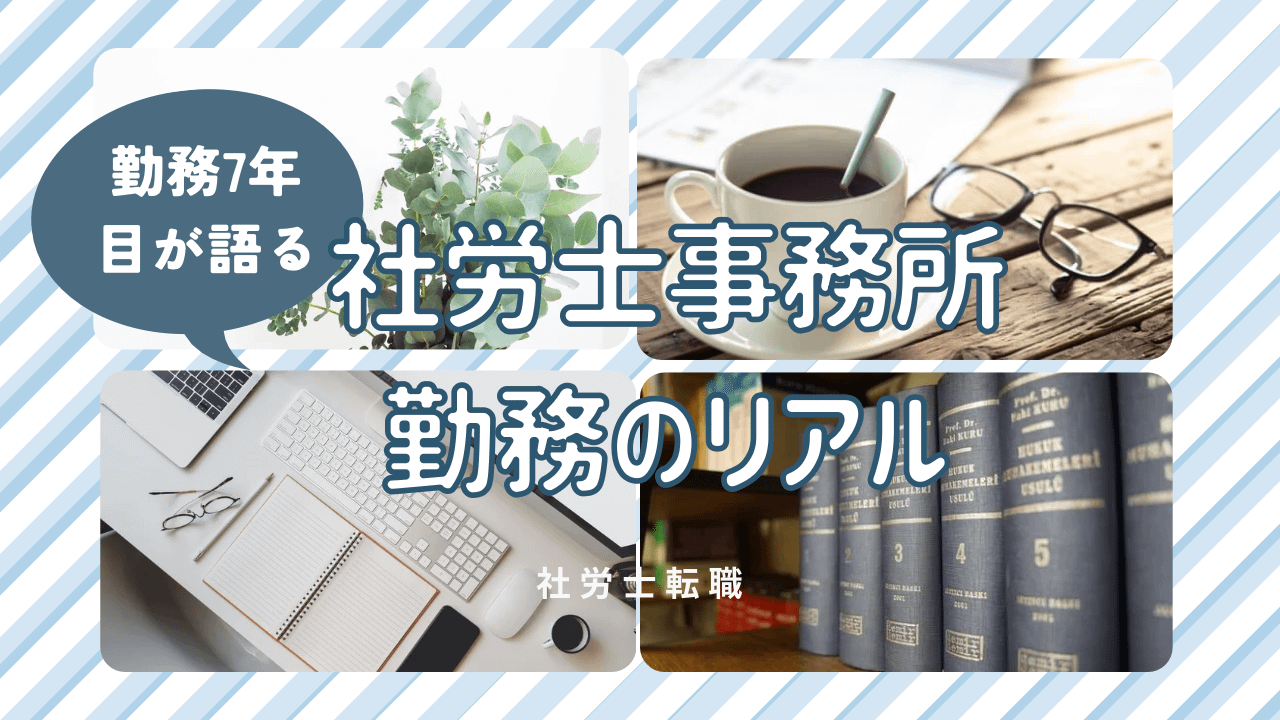
毎年、繁忙期が近づくたびに「やっぱり私には向いてないかも」と思ってしまうことがあります。給与計算や手続きに追われて、心も体も疲れきってしまう日々。
SNSでは華やかな社労士ライフが目に映るけれど、現実は地味で泥くさい作業の連続です。それでも、同じように悩みながら毎日を頑張っている仲間がいるから、乗り越えられることも多い。
そんな想いから、この記事を書きました。私の7年間のリアルな経験が、今つらさを感じている誰かの支えになれば嬉しいです。 特に、同じように社労士事務所で働く方や、これからこの業界を目指す方に届けばと願っています。
守秘義務のかたまりみたいなこの仕事では、「しんどい」「つらい」とすら、人にはなかなか言えないこともあります。
今回は、そんな私が「向いてないかも…」と思いながらも、それでもこの仕事を辞めなかった理由や、社労士事務所のリアルを正直にお話します。
社労士事務所の仕事内容とは?(給与計算、社会保険手続き、労務相談など)
社労士事務所での日々の業務は、非常に幅広く、専門性と実務力が求められる仕事です。社労士試験で学ぶ知識ももちろんベースになりますが、実際の現場で直面する業務には、机上だけでは身につかない「現場力」や臨機応変さが問われます。
給与計算は、単純な数字の集計ではなく、法改正や会社ごとの規程、雇用形態の違い、突発的な勤怠トラブルなど、毎月「例外」との戦いです。例えば、残業代の計算ひとつとっても、割増率の違いや手当の組み込み方など、会社によって細かなルールが異なり、一つひとつ丁寧な確認が欠かせません。
社会保険・労働保険の手続きも、入退社や育休・産休、扶養の変更など、人生の節目ごとに多様なケースが発生します。特に中小企業では、マニュアル通りにはいかないイレギュラーな対応を求められることが多く、「昨日まではなかった新しい課題」が突然降ってくることも珍しくありません。
助成金申請や就業規則の作成、雇用契約書のチェックも、法令遵守をベースにしつつ、会社ごとの事情や課題に合わせたカスタマイズが求められる分野です。「この書き方で本当に社員を守れるか」「この条文がトラブルの火種にならないか」と、慎重な判断と提案力が必要になります。
そして、経験を重ねるほど増えてくるのが「労務相談」です。現場で発生するリアルな悩みやトラブルは、社労士試験のテキストには載っていないものばかり。ハラスメントや解雇、メンタルヘルスの問題、働き方改革への対応など、相談内容は日々多様化しています。「このアドバイス一つで、その人の人生が大きく左右されるかもしれない」と思うと、常に緊張感を持ちながら、慎重に向き合う姿勢が欠かせません。
中小企業を支える社労士事務所にとっては、ルーチンワークだけでなく、毎日が「ライブ」であり、「想定外」の連続です。だからこそ、やりがいも大きい一方で、責任の重さや精神的な負荷も感じやすい仕事と言えます。
このような現場のリアルを知っておくことで、社労士の仕事に対する「理想」と「現実」のギャップを少しでも埋め、未来のキャリアをより確かなものにしていけるはずです。
辞めたくなる理由
社労士の仕事は、責任が重い。
特に給与計算や助成金業務は「お金」が絡むから、1つのミスで信頼を失うこともある。
検算しても不安で何度も見直したり、
「えっ、提出今日だったの⁉」とお客様から突然連絡がきたり。
肝が冷えた経験も、一度や二度じゃありません。お客様に迷惑をかけてしまい、落ち込んだ日も正直あります。
そしてもうひとつしんどいのが、「いつも何かに追われてる」感覚。
給与の締め日、納品日、助成金の期限…スケジュールはいつも「お客様都合」で動くことが多く、
こちらの段取りなんて吹き飛ぶような日もザラです。
それから、働き方にも葛藤があります。
社労士は「働き方改革」や「多様な働き方」を支援する立場なのに、
自分の職場ではテレワークやフレックスの導入が進んでいなかったり、帰りが遅くなるのが当たり前だったりすることに、正直モヤモヤすることも。
女性が多い職場で、子育て中の職員も多いのに、家とのバランスを考えた働き方ができていないことに不満を感じる日もあります。
それでも辞めない理由
それでも、私がこの仕事を辞めずに続けてこれたのは、
入社当初からずっと関わってきたお客様の存在が大きいです。
「事務員」として入った私をあたたかく受け入れてくださり、社労士資格を取得してからは、少しずつ「社労士らしい仕事」を任せてもらえるようになりました。
給与計算で大きなミスをして、号泣した日もありました。
もう信頼を失ったかもしれない…と思った顧問先さん。
それでも、変わらず「これからもよろしくね」と言ってくださって、今も一緒にお仕事をさせていただけています。
資格試験では学べない、生の現場、実務の難しさ。
それを何度も経験するなかで、知識だけでは対応できない「人との向き合い方」やトラブルへの対応力も少しずつついてきたと感じています。
そして今では、「この経験は、私にとって財産になる」と思えるようになりました。
まとめ
社労士の仕事は、ここ数年で大きく変化しています。
勤怠・給与のクラウド化、手続きの電子申請、そしてAIの登場。
これまで「人の手」でやっていたことが、どんどんデジタルに置き換わる流れは加速しています。
でも、どれだけツールが進化しても、
「目の前のお客様が何に困っているのか?」を汲み取るには、
やっぱり人としての経験や、積み重ねてきた実務力が必要だと感じます。
だからこそ私は、社労士としての知識とこれまでの経験を武器に、これからも学びを続けていきたいと思っています。
お客様にとって「相談してよかった」と思ってもらえる存在でいられるように。
そしてその一方で、自分自身の働き方や幸せも、忘れずに大事にしたい。
自分らしく働くこと。
そして、同じように日々がんばっている女性たちが、少しでも働きやすい環境で力を発揮できるように
まずは自分が実践して、表現して、伝えていきたい。
そんな思いを胸に、これからも社労士として、歩いていきたいと思います。