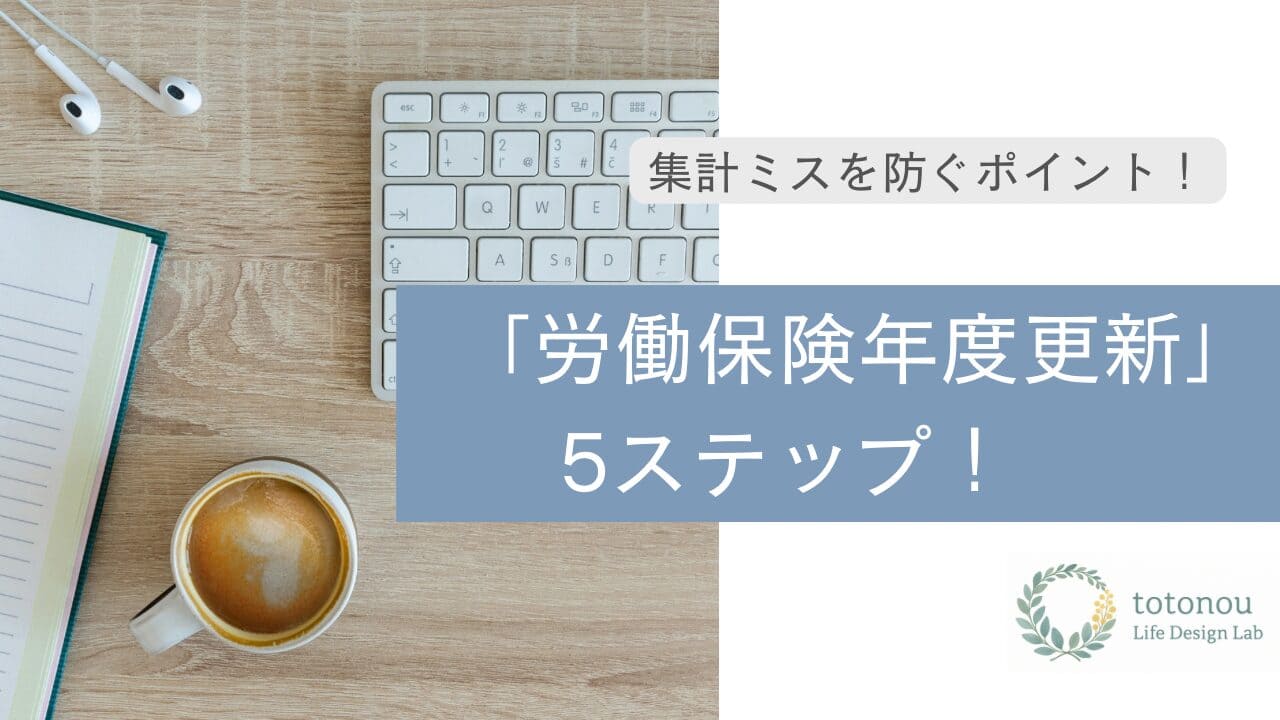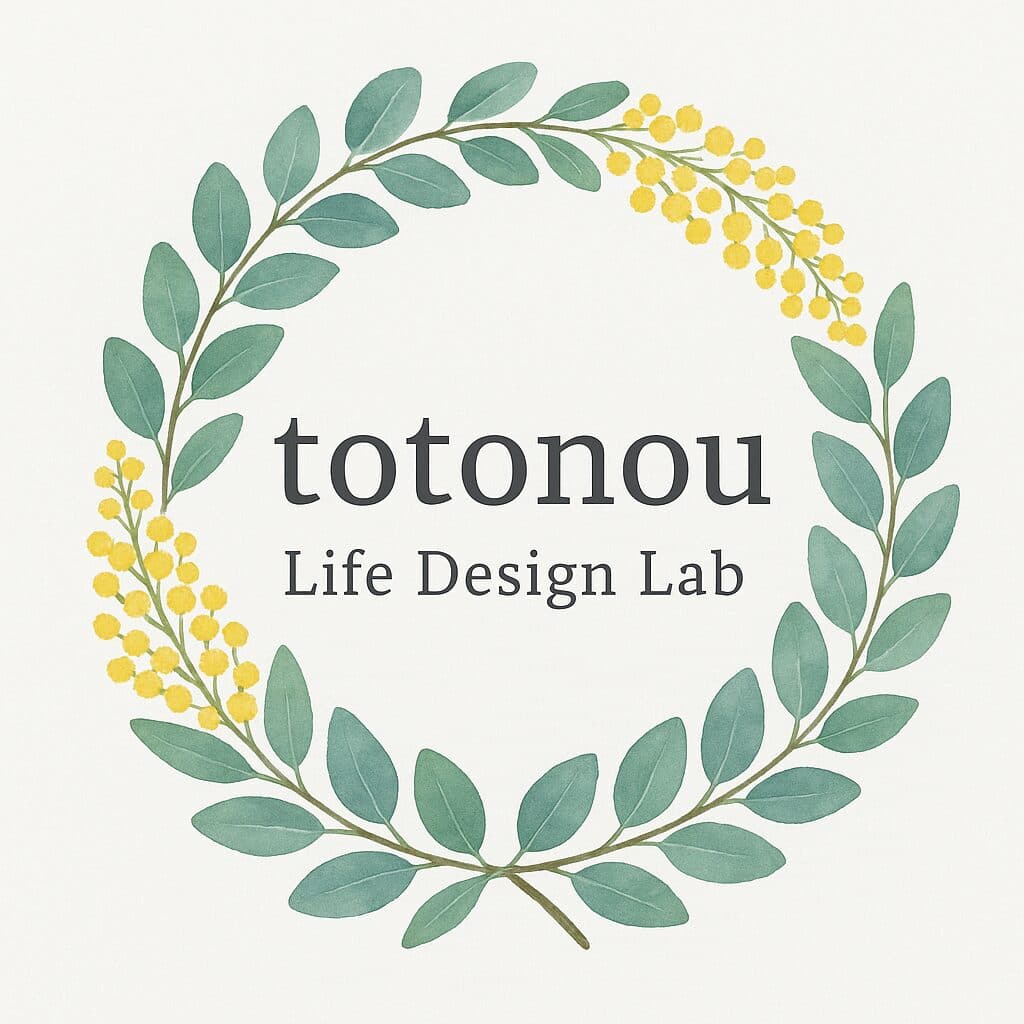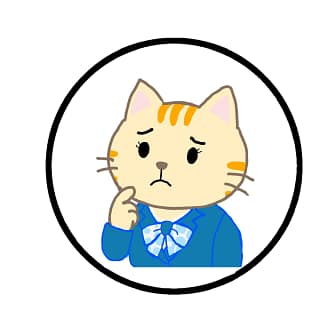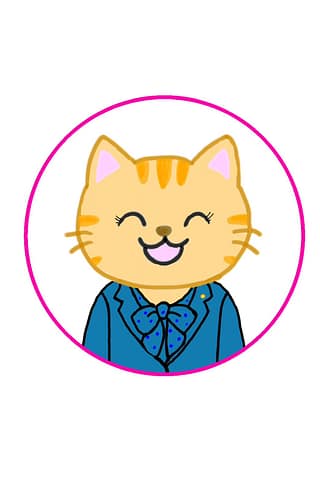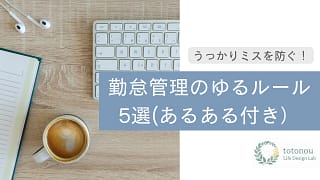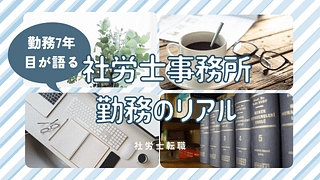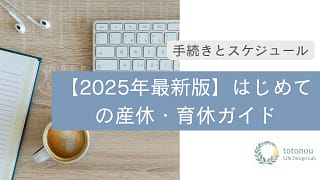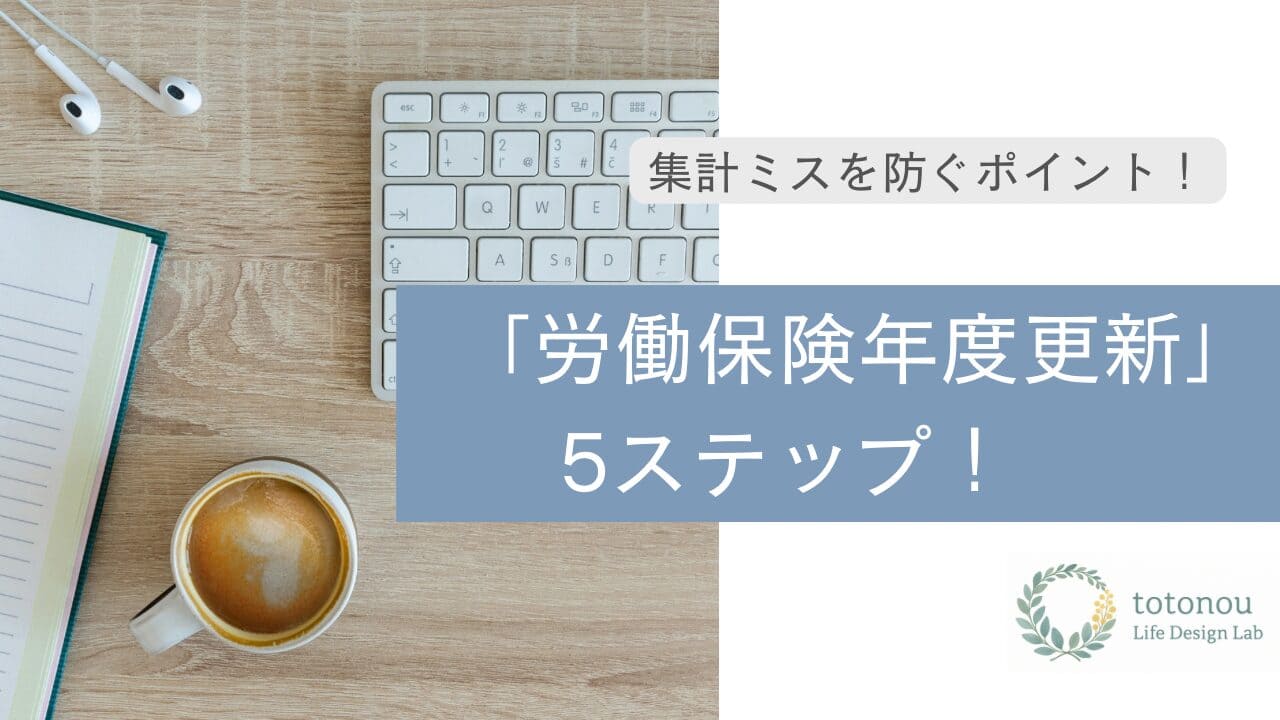
年度更新、ギリギリになって焦っていませんか?
毎年やってくるこの作業。月度ルーティン業務に追われて後回しになりがちですが、スムーズに終わらせるには「準備」と「確認」がすべて。
この記事では、一般事業の労働保険年度更新の社労士実務目線でおさえておきたい5つのステップと“よくあるミス”をまとめました。
STEP1:まずは対象者を正しく把握しよう
年度更新の最初のステップは、「対象となる従業員の把握」です。
ここがズレると、集計そのものが狂ってしまうので要注意。
雇用保険の被保険者って誰?
まずは、雇用保険の被保険者に該当するかどうかを確認しましょう。
週所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある人が基本の対象です。
正社員だけでなく、パート・アルバイトも条件次第で加入義務が発生します。
- 4月時点で未加入だった人も、年度途中で加入していれば対象
- 社保加入の有無とは無関係なので、念のため勤怠ベースで見直すのが◎
年度更新前に“加入・喪失の手続き漏れ”がないかチェック!
意外と見落としがちなのが、雇用保険の加入や喪失の手続きモレ。
年度更新は「届け出がされている人」を前提に進むため、手続きが漏れていれば、対象から抜け落ちてしまいます。
- 条件を満たしているのに加入していない人はいないか?
- 退職した人の喪失手続きは済んでいるか?
- スタッフの労働条件が変わったのに、変更届を出し忘れていないか?
年度更新の集計に入る前に、改めて雇用保険の加入・喪失状況を見直しておくのがベストです。
役員は基本的に対象外、でも親族は注意!
「うちは家族経営だから…」と気を抜いてはいけません。
たとえ親族でも、労働者性が高い親族が給与を受け取っているなら、雇用保険の対象になる可能性があります。
一方、会社の取締役など「役員報酬」を受け取っているだけの人は、原則として雇用保険の対象外です。
労災保険は「全従業員」が対象!
忘れがちですが、労災保険は雇用形態に関係なく、全員が対象になります。
たとえば、雇用保険に入っていない短時間アルバイトも、労災の対象には含めます。
顧問先から「このパートさん、労災もいらないですよね?」と聞かれたら要注意。給与を払っている以上、原則全員が対象です
雇用と労災で「対象人数が違う」こともある
これは実務でもよく混乱するポイント。
年度更新では、雇用保険・労災保険で別々に集計が必要です。
特に、20時間未満からスタートして、途中から雇用保険に加入したスタッフがいる場合は要注意。
加入タイミングによって、対象期間や集計方法が変わります。
給与ソフトの年度更新用の集計機能では対応しきれないこともあるため、手計算での確認が必要になるケースもあります。
STEP2:集計期間と申告期限を確認しよう
対象者を確認したら、次は「いつの賃金を」「いつまでに申告するのか」を押さえておきましょう。
年度更新は年1回しかない手続きなので、うっかり期間や期限を間違えないように注意が必要です。
対象となる賃金期間は「前年度4月1日〜3月31日」
年度更新の対象になる賃金は、前年の4月1日から当年の3月31日までに支払われたものです。
たとえば、令和7年度(2025年度)の年度更新なら、対象となるのは令和6年4月1日~令和7年3月31日の賃金です。
※賃金の「支払日」ではなく、「対象となる労働期間」に基づくこともあるため、3月勤務分を4月に支払っている場合などは特に注意しましょう。
申告期限は毎年「6月1日〜7月10日」
申告書の提出期限は、毎年6月1日から7月10日まで。
この期間内に、労働保険料の申告・納付までを完了する必要があります。
- 口座振替の会社は、申告が遅れると引落しに間に合わない可能性も!
- 賃金集計やチェックに時間がかかる場合は、早めの準備がカギ
誰が申告するかで、期限が前倒しになることも
顧問先が「事務組合」に労働保険の委託をしている場合、申告期限が前倒しになることがあります。
たとえば、「4月28日必着」など、事務組合ごとに締切が異なるため、事前確認が必須です。
- 委託先の事務組合の締切を把握しておらず、ギリギリになって焦る…
- 顧問先からの給与データが遅れて、事務組合に間に合わない…
STEP3:日頃の給与計算がカギ!集計の下準備
年度更新の集計でつまずかないためには、毎月の給与計算での「賃金の扱い方」がとても重要!
「総支給額をそのまま足せばOK」ではないため、日頃から“保険料対象賃金”を意識して運用しておくとスムーズです。
月例給与だけじゃない!賞与も含めて集計しよう
「毎月の給与分だけを集計して、賞与を入れ忘れていた…」
これは年度更新の集計ミスあるあるのひとつです。
労働保険の申告には、月例給与に加えて賞与も含めた年間の総額を対象にする必要があります。
支給タイミングが不規則な賞与も、必ず漏れなく集計しましょう。
総支給額=対象賃金ではない!
給与明細の「総支給額」がそのまま対象になるわけではありません。
労働保険料の計算に使うのは、「労働保険の対象賃金」であり、そこから対象外となる賃金を除いた金額を使います。
- 基本給
- 各種手当(職務手当、通勤手当、残業手当、住宅手当など)
- 賞与(臨時に支給されるものも含む)
- 時間外・休日・深夜割増手当
- 恩恵的に支給される手当(慶弔見舞金、結婚祝い金など)
- 実費弁償的な出張旅費・日当
- 解雇予告手当
- 退職金(退職後に支給されるもの)
STEP4:金額・人数のチェックポイント
集計が終わったら、そのまま申告書に記入せず、金額や人数に間違いがないかのチェックが欠かせません。
特に「労災」と「雇用保険」では集計のルールに違いがあるため、それぞれのポイントを押さえておきましょう。
労災と雇用で集計方法が異なることに注意!
同じ給与でも、労災保険と雇用保険では対象となる従業員が異なるケースがあります。
- 労災保険は「すべての従業員」が対象(雇用保険未加入者も含む)
- 雇用保険は、被保険者のみが対象
また、出向者や建設業の現場職員の扱いには特に注意が必要です。
| 対象者 | 注意点 |
| 出向社員 | ・保険加入している法人を確認 ・正しい集計先で申告(労災のみ出向先など) |
| 建設業現場職員 | ・「現場労災」対象の可能性あり ・特別加入制度の確認 ・営業など兼務していないかの確認 |
集計のルールを会社ごとに明確にしておくことが、ミスの防止につながります。
前年との大きな金額差は理由を確認!
前年に比べて大幅な金額差が出た場合、その理由をあらかじめ確認・記録しておくことが重要です。
税務調査や監査の際に説明を求められることもあるため、「なぜ増えた(減った)のか」を整理しておきましょう。
特に要注意なのが、労災・雇用保険料率の改定があった年です。
料率が変わっていないか、適用ミスがないかもチェックしておきましょう。
概算保険料は「今年の人員変動」も考慮して
最後に、今年の概算保険料を申告する際には「人員の増減」も見込んで金額を調整することが大切です。概算保険料が40万円以上(労災または雇用どちらか一方の場合は20万円)以上の場合、または事務組合に委託をしている場合は3回に分割することも可能です。
- 業務拡大など人員が大幅に増える予定→ 増加概算を検討
- 支店の削減など人員が大幅に減った → 概算額が大きすぎると還付金が多額になるリスクも
還付になった場合は、手続きの手間も発生するため、できるだけ実態に即した金額で申告するのがおすすめです。
STEP5:納付までが年度更新!期限厳守でトラブル回避
年度更新は「申告して終わり」ではありません。保険料の納付までがワンセットです。
毎年のルーチンだからこそ、うっかりミスや遅れが起きないように、改めてチェックポイントをおさらいしましょう。
保険料の納付は【7月10日まで】!期限厳守
労働保険の保険料は、会社が負担して納付する義務があります。
申告だけ済ませて納付を忘れていた…というのは避けたいミス。
- 納付期限:毎年7月10日まで
- 口座振替の場合は、第1期の引き落としが9月上旬の引き落とし
- 期日を過ぎると延滞金が発生する可能性も!
口座振替企業は“申告の遅れ”が即トラブルに
事前に口座振替を設定している企業の場合、申告が間に合わないと「振替不能」となり、
結果として延滞扱い・別途納付手続きが必要になるなど、手間もトラブルも増えてしまいます。
- できるだけ6月中に申告完了を目指す
- 関係者(経理や本社)とスケジュールを共有しておく
労働保険の口座振替は事前の申し込みが必要です!詳しくは厚生労働省のHPでご確認ください。
社労士事務所はクライアントへの郵送や電子申請のリスクも考慮!
社労士事務所で提出代行申請を行う場合は、提出方法ごとのタイムスケジュール管理が必要です。
郵送申請の場合:納付書をクライアントに届ける郵送日数も考慮して早めに対応
電子申請の場合:締切間際は混雑し、審査完了に数日かかることも。申告日=完了日ではないので注意!
労働保険料の口座振替以外にも各金融機関の“Pay-easy(ペイジー)”に対応したインターネットバンキングで電子納付も可能です!電子納付の際は、申請データ送信後の「収納機関番号」と「納付番号」をあらかじめ用意しておいてくださいね。
まとめ:年度更新は“事前準備”と“段取り”がカギ!
労働保険の年度更新は、毎年訪れる定例業務。
でも“慣れてるから”と気を抜くと、思わぬミスや漏れが発生します。
- 対象者を正しく把握しよう
雇用・労災の対象者に違いあり。加入・喪失の手続き漏れにも注意! - 集計期間と申告期限を確認 4月〜翌年3月の賃金を集計。
申告期限は「誰が申告するか」で違う! - 給与計算がカギ!集計の下準備 月給だけでなく賞与も。
対象賃金/対象外の見極めも重要! - 金額・人数のチェックポイント 前年との差異や人員変動、保険料率の改定にも目を配ろう。
- 納付までが年度更新!期限厳守でトラブル回避 7月10日納付期限。
口座振替や申請方法のタイミングに注意!
日々の給与計算や雇用手続きが、年度更新の正確さを左右します。
「まとめて一気にやる」ではなく、“日頃の積み重ね+スケジューリング”が肝心!
現場の事務スタッフさんや、社労士事務所の担当者さんにとって、
年度更新が“慌ただしいだけの季節行事”にならないよう、
準備と確認のコツを押さえておきましょう!