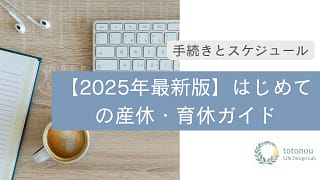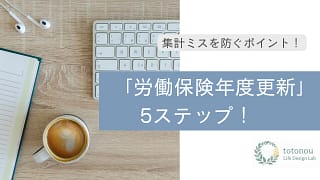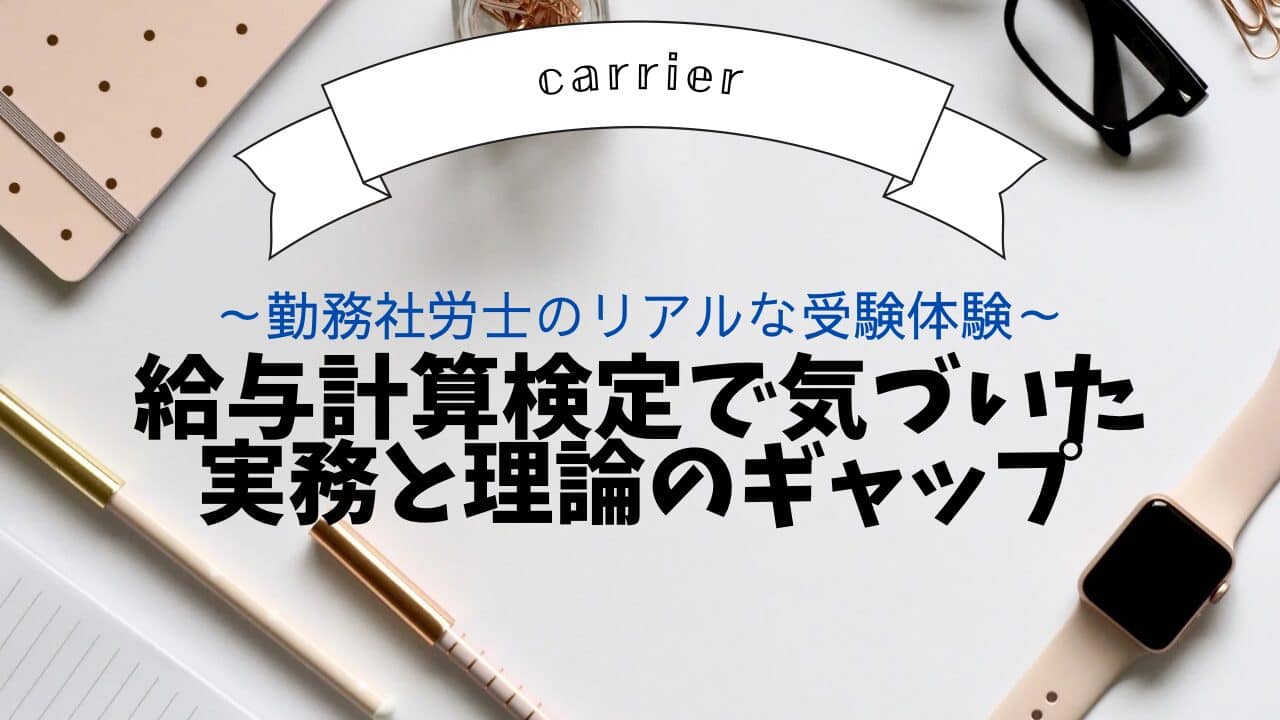
「給与計算って、毎月やってるけど…本当にこれで合ってるのかな?」
社会保険労務士事務所での実務歴7年の私でも、そんな不安を感じることがあります。その不安を解消するため、『給与計算検定』にチャレンジ!
最初は「勤務社労士が今さら資格?」と思っていましたが、勉強を通じて実務の根拠や法的背景を深く理解でき、素晴らしいリスキリングの機会となりました。
この記事では、資格取得のきっかけから勉強法、実務との違いまで、社労士にとってどのように役立つのか、率直な体験をお伝えします。ぜひ最後までお読みください!
1. 給与計算検定ってどんな試験?
「給与計算検定」は日本給与計算推進協会の検定試験で、給与計算の知識と実務能力を評価をする試験です。
試験は1級から3級があり、レベルに応じた能力が求められます。
■実施概要
| 級 | 実施日 | 受験料 | 出題形式 | 推定合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 年1回(11月) | 11,000円 | マークシート+記述式 | 約40~50% |
| 2級 | 年2回 (3月・11月) | 8,800円 | マークシート | 約60~70% |
| 3級 | 随時受験可能 | 10,000円 (受験料+WEB講座料) | WEB試験 | 約90% |
■1級:給与計算業務のリーダーとして必要な応用力や専門性の証明
1級では、幅広い労働法令や税務の専門知識をふまえ、複雑な給与体系や特殊な雇用形態、予期せぬイレギュラーなケースにも柔軟に対応できる高度な実務力が求められます。試験は全40問(知識問題30問・計算問題10問)で構成され、120分かけて解答。知識問題は四肢択一のマークシート方式(1問2点)、計算問題は記述式(1問4点)となっており、企業特有の諸手当や控除項目の取り扱いについても、的確な判断が下せることが期待されます。
■2級:給与計算の基本と実務力の確認
2級は給与計算業務の担当者や予定者が対象で、源泉所得税・社会保険料・賞与計算など、実務的な内容が中心です。試験は全40問(知識問題35問・計算問題5問)で構成され、120分かけて解答。知識問題は四肢択一のマークシート方式(1問2点)、計算問題も四肢択一のマークシート方式(1問6点)となっており、勤怠集計や保険料計算などの実践問題もあり、実務力を測る試験となっています。
■3級:Web講座+Web試験で気軽にチャレンジ
3級はWeb形式で実施され、試験時間は45分と比較的短時間です。全30問の試験は、知識問題25問(三肢択一)と計算問題5問(三肢択一)で構成されています。点数配分は、知識問題が1問3点(計75点)、計算問題が1問5点(計25点)の合計100点満点。給与計算の基礎知識を手軽に確認できる入門レベルの検定といえます。
■ どんな人に向いている?
- 社労士事務所の方業務の不安を解消し、基礎体力を上げたい方
- 人事・労務担当者 給与計算の仕組みをしっかり理解して、社員に分かりやすく説明できるようになりたい方
- 転職希望者実務スキルの証明として活用したい方
実務経験の有無を問わず、給与計算の深い理解と実践力が身につく検定です。
2. なぜ今「給与計算検定」を受けようと思ったのか?
「実務歴7年なら、今さら検定なんて必要ないのでは?」
そう聞かれることもあります。しかし実際には、毎月の給与計算業務の中で「これって本当に合っているのかな…?」と不安になることが少なくありません。
勤務社労士として登録後、同僚や後輩からの質問、顧問先からの細かい相談を受ける機会が増えました。「なんとなくこうしてきた」という処理では通用しないケースもあり、これまでの知識や経験を一度整理して、客観的に確認する必要性を感じるようになりました。
特に給与計算は、法改正や会社ごとの慣習、システムの特徴なども関係してくるため、意外と“自己流”になりやすい業務です。あいまいな知識のまま回答してしまうことは、自分にとっても相手にとってもリスクとなります。
実務をこなすだけでは身につきにくい、根拠や制度の背景をきちんと確認し直し、給与計算のその先にある「顧問先への付加価値提供」につなげたい――そんな思いから受験を決意しました。
社労士受験仲間が一緒に受験しよう!と誘ってくれたおかげで試験までのモチベーションもキープできました。誰が一番点数をとれるかのビールを賭けた勝負・・
3. 実務と給与計算検定で見えた新たな気づき
給与計算検定で勉強して気づいたのは、実務と理論には意外な違いがあるということです。普段の仕事では、給与計算システムに頼ったり、前からのやり方をそのまま続けたりしがちですが、検定では「なぜそうするのか」という理由が大切になります。
特に勉強になったのは、法律の言葉や制度をきちんと理解することです。例えば、「この手当は残業代を計算するときに含めるべきかどうか」といった判断をするときも、しっかりとした理由が必要になります。
また、給与計算の知識だけでなく、労働法・税金・社会保険など、関連する分野の知識も必要です。これらを学ぶことで、単に計算するだけでなく、給与に関する仕組み全体が分かるようになりました。
この検定は、社労士として仕事をする上でとても役立つものでした。「なぜこの処理をするのか」「どの法律に基づいているのか」といった背景が分かるようになり、会社からの質問にも自信を持って答えられるようになったのです。
日々受ける「ちょっと教えて」という質問にも、以前より分かりやすく説明できるようになり、自分が成長したと実感しています。
4. 勉強法・使った教材・スケジュール感
私が給与計算検定2級の勉強を始めたのは、受験の約1か月前。
1日あたりの勉強時間は30分程度と、かなりミニマムな学習スタイルでした。
とはいえ、すでに社労士試験の勉強を終えていたこともあり、内容の難易度としてはそこまで高くないと感じました。労働基準法や社会保険制度など、基本的な枠組みを知っていれば、スムーズに進められると思います。
ただし、要注意なのが計算問題。
支給控除の内訳や、手当・割増・年調に関する計算などは、実務経験がないと時間がかかるかもしれません。社労士試験とは異なる「手を動かす系」の問題が多く、地味に引っかかりやすい部分です。
■ 使用した教材・勉強スタイル
私は、公式テキスト(1冊)のみを使用しました。
実は、1年型落ちしたものを中古で購入したのですが、給与計算は法改正の影響を受けやすいため、不安な方は最新年度版の購入をおすすめします。とくに社会保険料率や非課税限度額など、数値を問われる問題も出るため、古い情報のままだと不利になる可能性があります。
また、公式テキストの問題量がかなり少ないのがネックだったので、私はYouTubeで解説動画を見ながら補強していました。
計算の流れや考え方を音声と画面で確認できる動画は、短時間の勉強にはぴったり!私はとくに賞与計算を繰り返し解いていました。
■ 忙しい勤務社労士におすすめの“時短勉強法”
- スキマ時間にYouTubeでインプット(音声だけでもOK)
- テキストは1冊にしぼって繰り返す
- 計算問題は「見るだけ」よりも「手を動かして解く」がおすすめ
忙しい中でも、「試験勉強=長時間必要」という思い込みを手放すことが大切。
30分×30日でも、意外と知識は定着するものです。
5. 実際に受けてみた感想&難易度
まず、試験形式はマークシート方式で、全体的に落ち着いた雰囲気。社労士試験のようなピリピリ感はなく、飲み物の持ち込みもOKでした。
電卓の使用も可能で、おすすめは時間計算機能(60進法)が使える電卓です。所定労働時間や残業時間の計算をする場面では非常に便利なので、持っている方はぜひ持参を!
加えて、腕時計も必須アイテム。私が受けた会場には時計がなかったため、試験中に現在時刻や残り時間がまったくわからず焦りました。腕時計がないと時間配分がかなり難しくなるので、当日忘れずに準備しておきましょう(スマホは使用不可です)。
私が受けた会場は、駅から徒歩15分ほどかかる、厳かな雰囲気の会館。
「まぁ地図通り行けば大丈夫でしょ」と軽く見ていたら、思った以上に距離があり、当日は走ってギリギリ間に合うというハプニングも…。
会場によってはアクセスが悪いこともあるので、事前の下見 or 早めの出発は必須です!
■ 思ったより取り組みやすかった!
試験を受けて感じたのは、「思ったより計算問題が少なかった!」ということ。 私はもっとガッツリ計算系を出されるかと思っていましたが、実際は1問6点×数問のみで、割合としてはそこまで多くありませんでした。「思ったより取り組みやすかった!」ということに加えて、試験の合格率の高さも魅力的なポイントです。実際、2級の合格率は約70%と高めなので、これから社労士試験に挑戦する方にも弾みをつける意味で、挑戦しやすい資格試験といえるでしょう。
…が、ここで油断すると危険!
この計算問題の配点は1問あたり6点と高く、間違えると一気に痛手です。
苦手意識のある方ほど、「ここだけは絶対に正解する」くらいの気持ちで取り組むのがベター。
■ 合格のポイントはここ!
- 公式テキスト+YouTubeなどの補強教材でOK
- 配点が高い計算問題は絶対に落とさない
- 会場は余裕をもって到着する!(重要)
- 腕時計は必ず持参!時計のない会場もあります
- マークミス対策として、最後の見直しを忘れずに!
ちなみに私は、最後の見直しでマークずれが3つも発覚して冷や汗…笑
問題番号とマークの位置ズレ、意外とやりがちなので気をつけてくださいね。
6. まとめ|”実務と理論、両方を深める機会に”
給与計算検定を受けた最大の収穫は以下の3点です
1.実務の「なぜ?」がクリアに
検定を通して、日々の実務でなんとなく処理していたことに、法的な根拠があると実感しました。
- 「月給者の日割計算はなぜ〇〇.〇日なのか」
- 「カレンダー日数で割ると違法になる理由とは」
- 「欠勤控除と賃金の一部控除の違いは何か」
どれも、正しく理解すれば「説明できる実務」に変わります。今後の処理やアドバイスにも自信が持てるようになりました。
2.知識と実践の融合
経験者だからこそ、実務で培った感覚と理論的な裏付けが結びつき、より深い理解につながりました。
3.さらなる成長への意欲
「今だからこそ、意味がある」—そんな検定でした。
11月は1級にチャレンジする予定です。
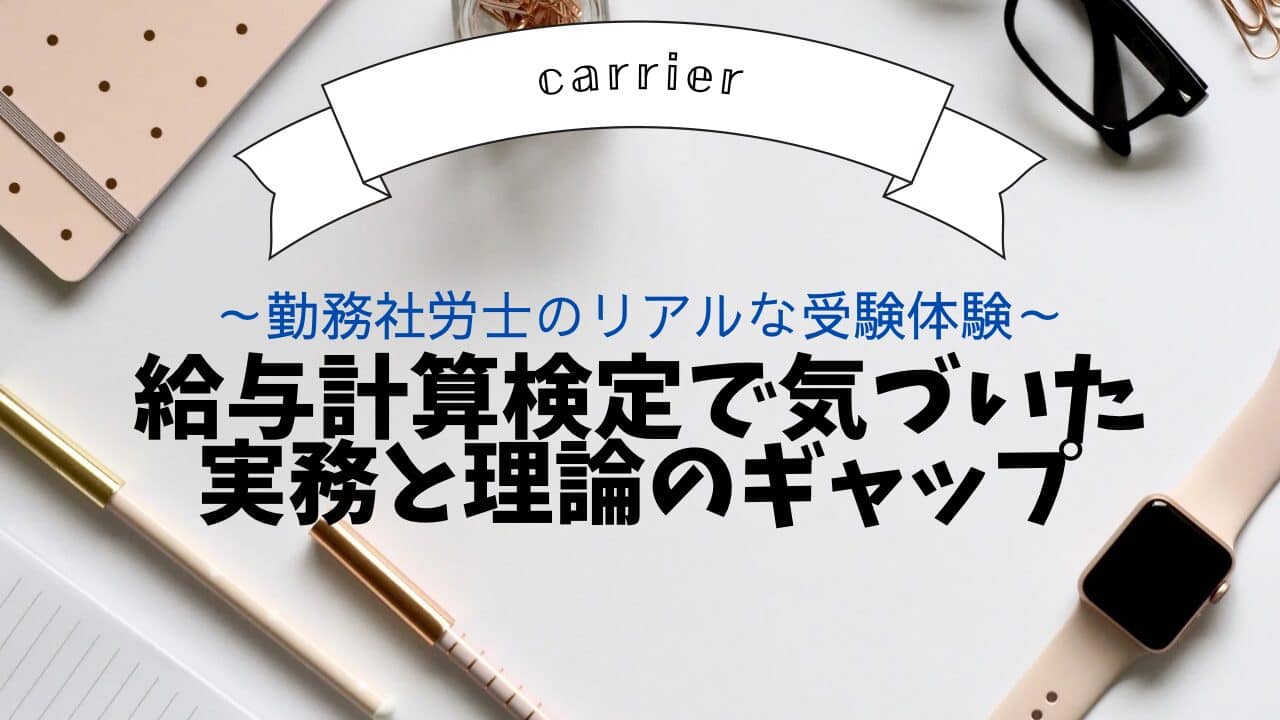
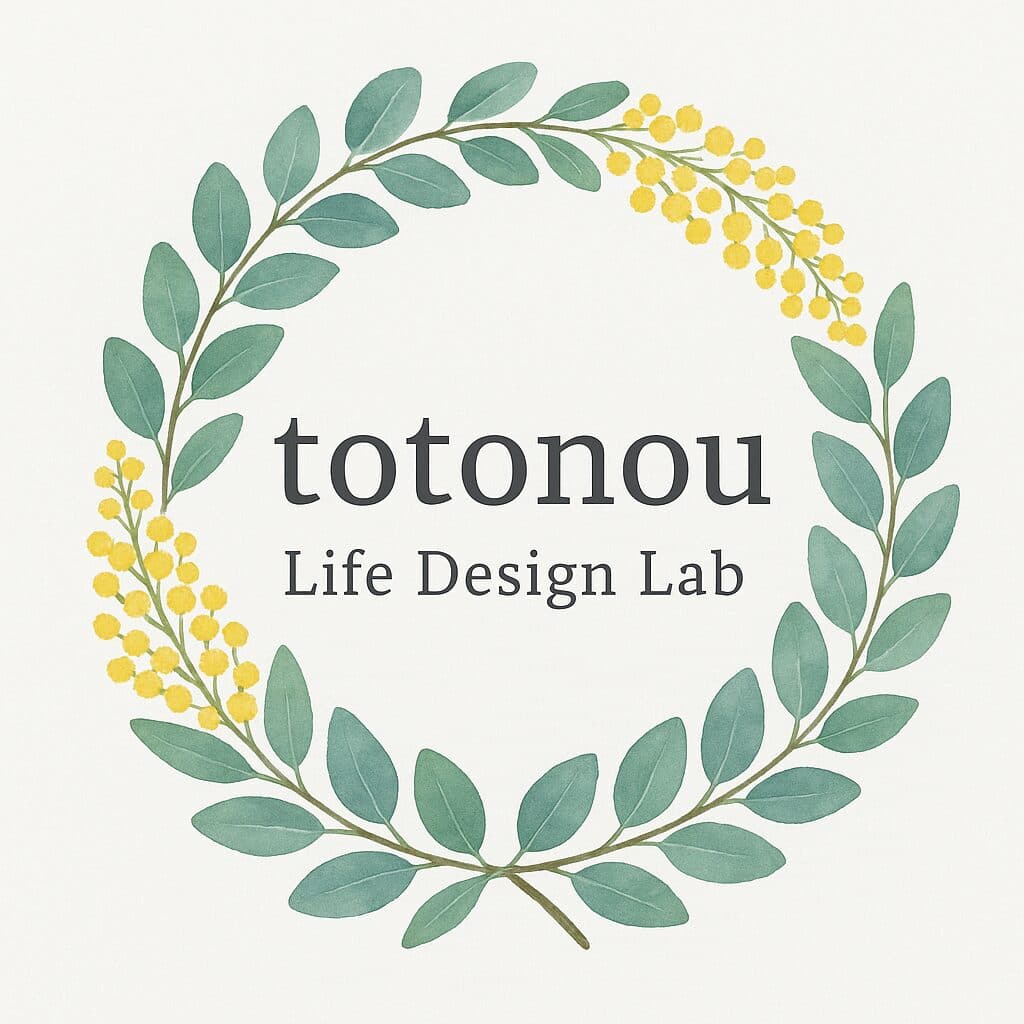


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47eceaaa.eb0c505d.47eceaab.4e4ce7dd/?me_id=1269033&item_id=10042119&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftarosdirect%2Fcabinet%2Fns%2Fns-casio%2Fns-mw-c20c_00.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)