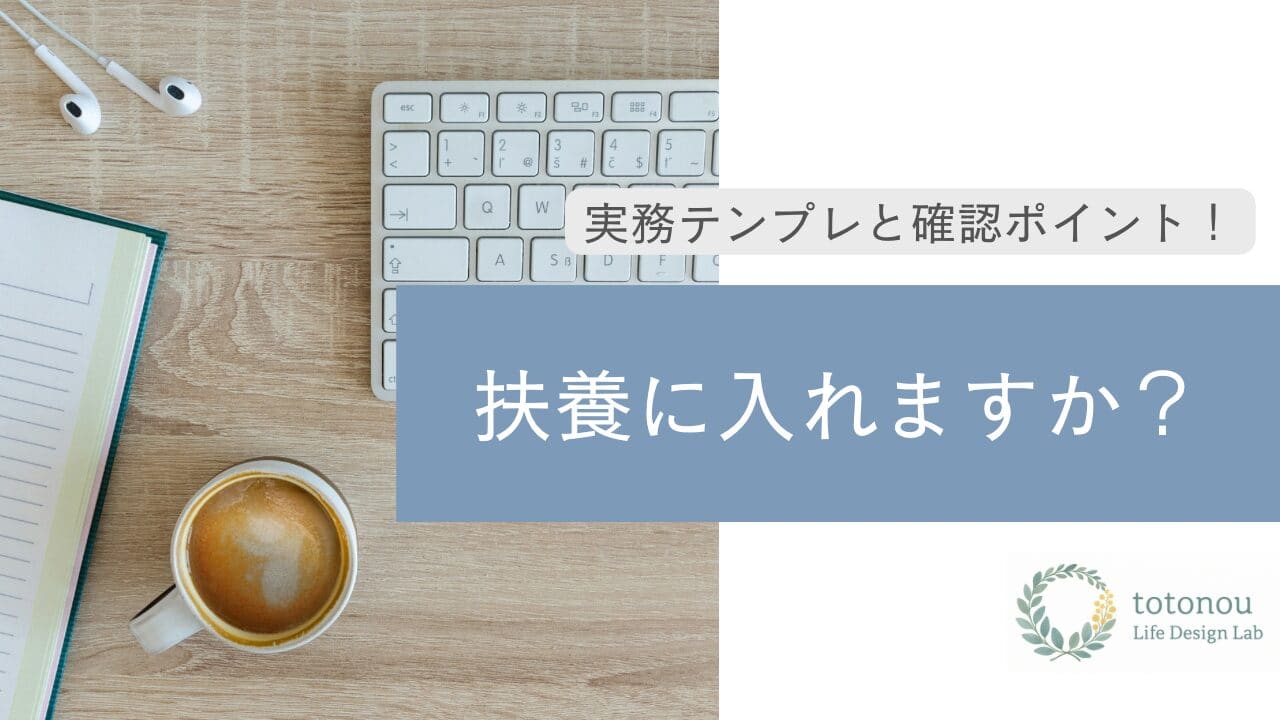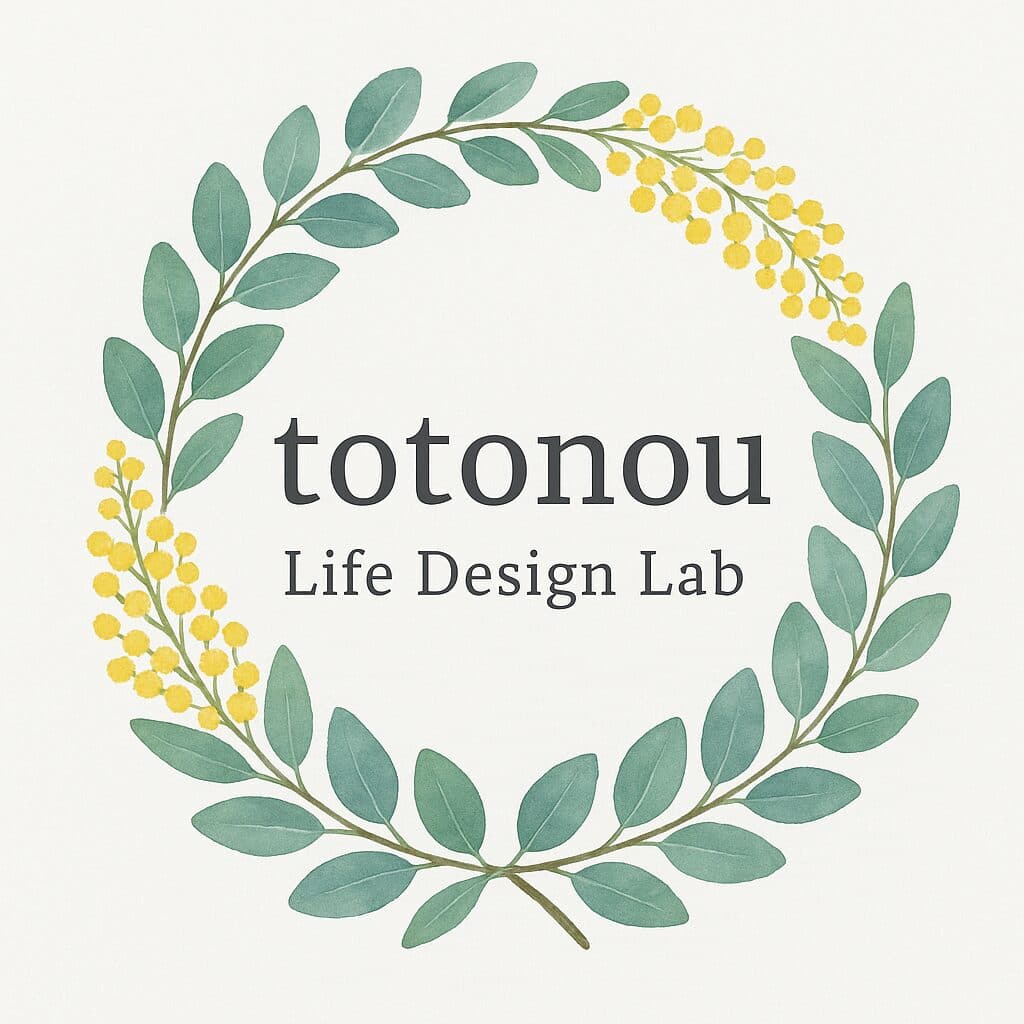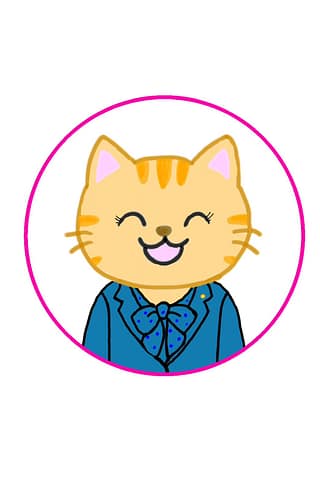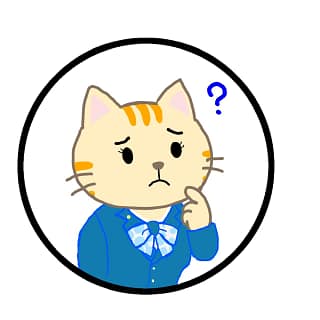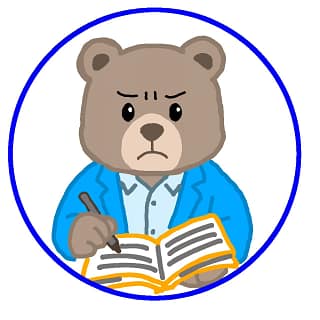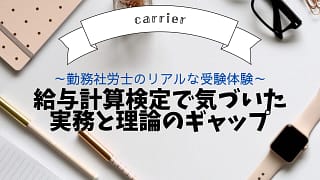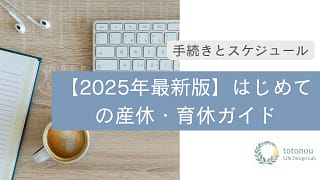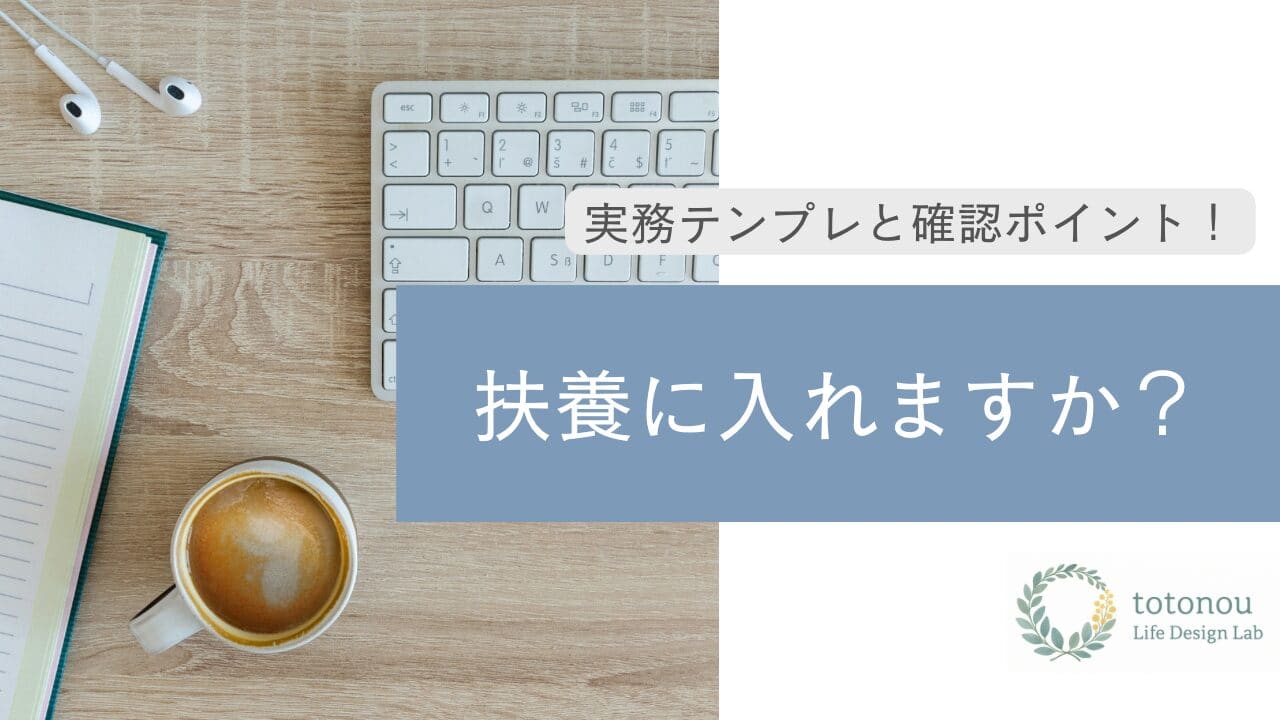
「扶養に入れますか?」
社労士事務所で働いていると、常日頃に聞かれるこの質問。
実はこの「扶養」という言葉、健康保険・年金・税金でそれぞれ意味も基準も違います。一見シンプルな質問に見えて、実はかなり複雑。そして、説明する側にも“わかりやすく伝えるスキル”が求められるポイントです。
「収入が〇万円以下なかOKなんでしょ?」と思っていたら、実は入れないことも…。
このページでは「扶養に入れる?入れない?」の判断ポイントや、実務で確認すべきポンとをわかりやすく&サクッとまとめています。
「毎回ググってる…」という方や、「これから社労士実務に入る予定」の方にも役立つよう、実務ハックとしてまとめました!
1. 「扶養に入れる条件って?よくある質問への答え方」
「うちの奥さん、今年も扶養に入れますか?」
「息子が大学生なんですけど、扶養にできます?」
「パートを始めた妻、どこまで稼いだら扶養から外れるんでしょうか?」
毎年のように、何度も何度も聞かれるこの質問。
「扶養に入れますか?」というのは一見シンプルな問いかけのようで、実はかなり奥が深いテーマです。
なぜなら、“扶養”と一言で言っても、
- 社会保険上の扶養
- 税金(所得税)上の扶養
という2つのまったく別の考え方があるからです。
しかも、それぞれに年収の目安や同居・仕送りの有無など、細かな条件がついてきます。
そして何より、「誰を」「何のために」扶養に入れたいのか?
つまり、
- 扶養に入れたい人は誰なのか(配偶者?子ども?親?)
- その人の収入や働き方は?
- そもそも質問している人は“税金”と“社会保険”のどちらを聞いているのか?
こういった要素を整理しないと、正確な答えを出すことはできません。
とはいえ、実務の中では「要点を押さえた、わかりやすい伝え方」が求められますよね。
この記事では、実務でよくある“扶養に入れますか?”という質問への答え方や、チェックすべきポイント、伝え方のコツをまとめていきます。
まずは、「扶養とは何か?」をシンプルに整理するところから、一緒に確認していきましょう。
2. 「扶養」とは?そもそも何の扶養?
「扶養に入れますか?」という質問を受けたとき、まず最初に確認すべきなのは、
それが何の扶養についての話なのかということです。
実は、“扶養”には大きく分けて次の3つがあります。
【1】健康保険(社会保険)上の扶養
- 被扶養者になることで、保険料の負担なしに健康保険に加入できる制度
- 主に会社員の家族が対象で、「年収130万円未満」などの収入や生計維持条件あり
【2】年金(厚生年金)上の扶養
- こちらは「扶養」という名称は使わないものの、配偶者が厚生年金に加入している場合、国民年金保険料を払わずに済む仕組み(=第3号被保険者)
- 主に専業主婦(夫)や、パートタイマーなどが対象
【3】税金(所得税)上の扶養
- 扶養控除や配偶者控除など、所得税の軽減を受けられる制度
- 「年収103万円以下」などの基準があり、扶養家族が多いほど所得税が安くなる
このように、一言で「扶養」と言っても、対象や効果、年収の基準がすべて違うんです。
たとえば――
- 健康保険上は扶養に入れるけど、税金上は入れない
- 税金上の扶養にはできるけど、健康保険では外れる可能性がある
こんなパターンも、実務ではよく出てきます。
質問されたときは、いきなり答えるのではなく、こう聞き返しましょう。
社会保険上の扶養の話ですか?それとも税金上の扶養の話ですか?
このひとことだけで、話の方向性がグッとクリアになります。
次のセクションでは、それぞれの“扶養”について、より詳しく・実務で使える形で見ていきましょう。
3. “扶養に入れますか?”と聞かれたときの回答テンプレ
“扶養に入れますか?”という質問は、誰からもシンプルに聞かれがちですが、背景にある状況はそれぞれ異なります。
ここでは実際によくある質問パターンごとに、回答テンプレート+実務的な補足をまとめました。
■ケース①「パートに戻ったけど、扶養に入れますか?」
▶よくある聞き方:
久しぶりにパート始めたんですけど、夫の扶養に入れますか?
▶テンプレ回答例:
健康保険の扶養の場合は、年収の見込みと勤務先の社会保険と働き方によります。
- 年収の見込みが130万円未満(または106万円未満)かどうか▶いわゆる「年収の壁」
- 週の労働時間がフルタイムの3/4未満か
- 勤務先に社会保険の加入義務があるか などを確認
- パート復帰で「収入見込みが月10万以下」で「短時間勤務」なら、扶養に入れるケースが多いです
厚生労働省:年収の壁・支援強化パッケージ「106万の壁」・・・お勤め先の企業規模によって、健康保険・厚生年金保険への加入義務が発生する年収
※令和6年10月から「従業員51人以上」の会社にお勤めの方にも適用を拡大
※加入要件は企業規模以外に、月額賃金8.8万円(年収計算で約106万円)、週の労働時間が20時間以上などがある。「130万の壁」・・・上記以外のお勤め先の場合に、
国民健康保険や国民年金の保険料の支払いが発生する年収
「年収の見込み」は、手続き時点から将来に向けた見込み額で考えます。
税法上の扶養とは基準が異なるので、実際の年収(前年の額など)を答えないよう注意!
協会けんぽと健保組合では、審査の厳しさが違うこともあるので、念のため確認を◎
■ケース②「息子が大学生なんですけど、扶養にできます?」
▶よくある聞き方:
「今、うちの子バイトしてるんですけど、それでも扶養に入れますか?」
▶テンプレ回答例:
税金上の扶養は可能です。健康保険の扶養についても、仕送りや収入の状況によっては扶養に入れることがあります。
- 学生の場合、税金上の扶養(扶養控除)は年収が150万円以下で、生計を一にしていれば控除対象
※令和7年度税制改正あり詳しくはこちら - 健康保険の扶養は「別居の場合は仕送りが収入より多いか」がポイント → 別居でも仕送りしていればOKなケースあり
- 20歳以上は国民年金保険料の納付義務がある(「学生納付特例制度」というしくみも案内!)
▶確認ポイント:
■ケース③「パートを始めた妻、どこまで稼いだら扶養から外れますか?」
▶よくある聞き方:
「妻が働き始めたんですけど、扶養って外れるんですか?」
▶テンプレ回答例:
年収130万円を超えると、健康保険の扶養から外れる可能性が高いです。税金上は123万円・160万円など段階があります。
- 健康保険は「130万円の壁」または「106万円の壁」(勤務先の条件による)
- 妻が社会保険加入対象になれば、扶養からは外れる
- 所得税は「配偶者控除」→123万円、「配偶者特別控除」→160万円、201万円まで段階的
※令和7年度税制改正あり詳しくはこちら
▶確認ポイント:
■ケース④「別居の両親を扶養できますか?」
▶よくある聞き方:
仕送りしてる親がいるんですけど、社会保険の扶養に入れられますか?
▶テンプレ回答例:
社会保険の扶養は、収入や生活の援助状況によって判断されます。
▶実務の補足:
- 収入条件:一般的な場合▶年間収入が130万円未満
60歳以上の親または障がい者の場合▶年間収入が180万円未満 - 仕送り条件:仕送り額が親の収入額を上回っていること
- 生活援助の実態があること
- 社会保険手続きの際は、仕送りの証明書類(通帳の写しなど)が必要な場合が多い
▶確認ポイント:
4. 社会保険と税金、それぞれの扶養の条件と確認フロー
【社会保険上の扶養】 基本の判断基準
| 判定ポイント | 内容 |
|---|---|
| 年収基準 | 年間収入が130万円未満(60歳未満または障害者は180万円未満)かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること |
| 被保険者との関係・同居要件① | 被保険者の直系尊属(父母、祖父母等)、配偶者(事実上を含む)、子、孫、兄弟姉妹 ▶同居でなくてもOK(仕送り等の援助実態が必要) |
| 被保険者との関係・同居要件② | 上記①以外の3親等内の親族、事実婚の配偶者の父母および子 ▶同居要件あり |
実務ポイント①:収入は「今後の見込み」で判断
「今年は収入が少ないけど、来月から増える予定…」
→ 健康保険では、過去実績ではなく“今後の見込み収入”で判断します。
たとえば、月収が継続して108,000円を超えると見込まれる場合、年間130万円を超えると判断され、扶養不可になる可能性が高いです。
実務ポイント②:勤務先に社会保険があると加入義務が優先される
もし扶養に入りたい本人の勤務先に社会保険の適用義務がある場合、
たとえ年収が130万円未満でも「本人が社会保険加入者」となり、扶養には入れません。
▼加入対象となる目安(いわゆる“106万円の壁”)
- 従業員数:51人以上
- 週の勤務時間:20時間以上
- 月収:88,000円以上
- 雇用期間見込み:2か月超
- 学生でない
- 扶養に入りたい家族の今後の月収と年収の見込み
- 勤務先の規模(従業員数51人以上かどうか)
- 被保険者と扶養に入れたい家族との続柄+同居か別居か
扶養手続きの地味キャラ?「国民年金第3号」ってなに?
「第3号って聞いたことあるけど…何だっけ?」という方も多いかもしれません。
実はこれ、**年金制度上の“扶養扱い”**のことなんです!
第3号被保険者とは、**厚生年金に入っている被保険者に扶養されている配偶者(主に専業主婦・主夫や一部のパートさんなど)**のこと。
この人たちは、自分で年金保険料を払わずに国民年金に入っている扱いになります。
ただし!注意しておきたいのが、国保組合や市町村国保には「扶養」という概念がないこと。
とくに国保組合と厚生年金の“ミックス型”の会社の場合は要注意!「健康保険上の手続きはできているのに、年金の届出が抜けていた!」というケース、実はけっこうあるんです。
ミックス型の会社は、健康保険は一緒に加入する配偶者は被保険者扱い(≠扶養)、厚生年金は扶養扱い(=第3号)となります。
この場合、「国民年金第3号関係届」の提出が必要になります。
扶養手続きのときは、年金の第3号届もワンセットで忘れずに!
会社の手続き担当や社労士に、ひとこと確認しておくと安心ですよ。
【税法上の扶養】(配偶者控除・配偶者特別控除)
扶養に入ってるから、税金も安くなるよね?
よく聞くこのフレーズ、実は**“税金の扶養”**のことを指しています。中でも代表的なのが、配偶者控除と配偶者特別控除。
簡単に言うと、夫(または妻)の年収から一定額を差し引いて税金が軽くなる制度です。
いわゆる123万円の壁(=配偶者控除の対象)と160万円の壁(=配偶者特別控除の段階的減額)がそれにあたります。※令和7年度税制改正あり詳しくはこちら
たとえ税扶養には入れても、社会保険では扶養に入れないケースもあります(その逆もしかり)。
紛らわしいけど、それぞれの基準が違うからこそ、扶養の種類ごとにチェックが必要なんです。
5. まとめ:扶養に入れるか迷ったときの判断ポイントと対応の考え方
「扶養に入れますか?」という相談には、制度の違いを理解した上での対応が大切です。押さえておきたい3つのポイントはこちら。
「扶養=万能な言葉じゃない」ことを伝える
健康保険、年金、税金で「扶養」の意味は異なります。
→まずは「どの制度についてのご質問でしょうか?」と制度の確認から始めましょう。
実務では“断言より確認項目の提示”が大切
判断は健保組合や税務署が行うため、「○○だから大丈夫」と断言はNG。
→「現時点の情報では〇〇の可能性が高いですが、最終的には〇〇次第です」と柔らかく伝えるのが安心感につながります。
予測で断言しない姿勢が大事
年収見込みが確定していない場合、「たぶん大丈夫」はリスク大。
→「収入が増えたら再確認が必要です」など、一歩引いた対応が信頼を生みます。
「即答しない」「整理して伝える」この2つを意識すれば、実務でもブレずに対応できます!